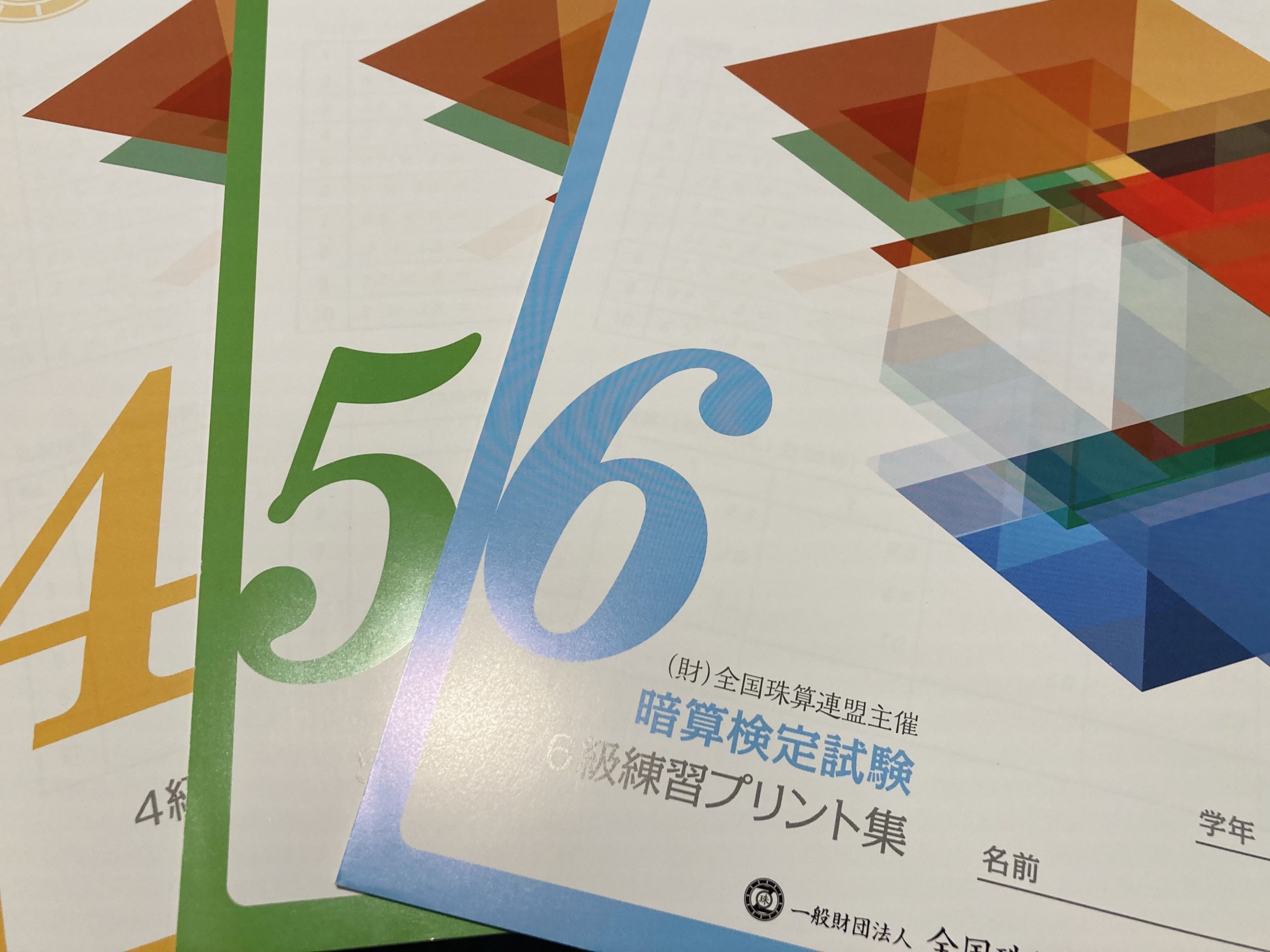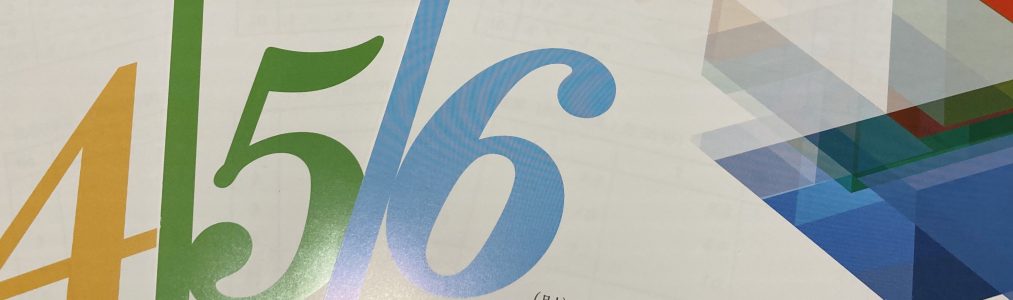こんにちは、栗崎です。
今日はハロウィン前の最後の土日。
街を歩くと仮装をしてる子供達をちらほらと見かけました。
あいにくの雨天でしたが、お菓子を抱えてハロウィンを楽しんでいる姿にほっこりしました。

さて、今日は暗算の話。
そろばんを始める理由の一つに
中学入試に向けて計算力を鍛えたい、と始める方がいます。
その際に「どこまでの級に進めれば良いでしょう?」と聞かれることがあります。
当教室では暗算は6級からスタートしますが、
ホップ、ステップ、ジャンプが完了して
9.10級の練習に入った段階から暗算チャレンジ、という級の前段階の暗算練習テキストに入ります。
暗算チャレンジは全部で6冊、
1〜4は見取暗算(2桁2口〜3口)
5.6は乗暗算(1桁✖️2桁)
を練習します。
この6冊が終わると暗算6級に入ります。
暗算6級は
乗暗算 1桁✖️2桁
除暗算 2桁or3桁➗1桁(答えは2桁になります)
見取暗算 2桁3口
3分計測で乗・除暗算20問ずつ、見取暗算10問を解く難易度になります。

さて、ここで中学入試の算数の話をします。
出題の傾向としまして、
大問の一つ目が計算問題となるのですが、
いかに早く正確に解くかが鍵となります。
例題を挙げていきます。
14×7-29-57÷3 =
(東洋英和女学院中学部2022)
シンプルな計算問題です。
計算の順序を間違わなければ
暗算6級レベルでさくさくっと解ける問題です。
(297+328-142)÷(29×7-14×13)=
(横浜雙葉中学高等学校2025)
後半の括弧の中に2桁×2桁が登場しますが
実は計算の工夫をすれば
暗算6級レベルの問題に置き換えられます。
29×7 はそのままで。
14×13 の14をバラすと7×2×13 と同じになります
ここで2×13を先に計算すると
14×13=7×2×13=7×26と 置き換えられます
後ろの括弧の中は
29×7-7×26 どちらも同じ7をかけているので、
(29-26)×7 と同じになります
括弧の中を計算すると3×7
さてここで前半の括弧をみます
(297+328-142)
愚直に計算してもいいですが、
楽したいので
300を使っていきます
300-3=297
300+28=328
150-8=142
こんな感じで数字を分解して、括弧に戻します
先に300と150を計算して
残りの3、28、8をまとめて計算しますと
(300-3+300+28-150+8)=(450+33)
ところで気づきました?
450と33 どちらも3の倍数
この足した数字(前半の括弧の中)、
あとで3×7で割るんですよね
分子が450+33で分母が3×7
の分数計算と同じです
なので先に3で割っちゃいましょう
(450+33)÷(3×7)=(150+11)÷7=161÷7
最後に出たわり算は
暗算6級レベルの問題に落とし込めます。
このように一見複雑そうにみえる計算問題も
工夫すれば最終的に暗算6級レベルの問題でささっと
計算が可能です。
なので中学受験に向けてどこまで級を取得しておくと安心かと聞かれましたら
私は大抵6級がしっかり解けるレベルでしたら安心です、と答えることが多いです。
ちなみに暗算2級から2桁×2桁のかけ算、2桁のわり算、
2〜3桁のたし算問題が出てくるので
2級以上のレベルでしたら
中学入試の最初の計算問題を
ゴリ押しで解くことも出来ます。
(作問者側の意図からは外れるのでお勧めはしませんが)
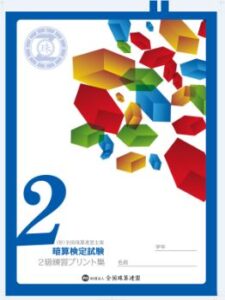
ともあれ基本の問題となる最初の計算問題において、
正確率とかかる時間が早いほどプラスになるのは間違いありません。
そろばんを始める際の一つの指標として
まずは暗算6級取得目指すという目標を立てるのも
良いかもしれません。
栗崎